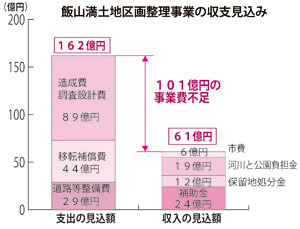6月議会では、東日本大震災の復旧関連補正予算などが審議されました。議案に対する質疑の概要を報告します。
■震災で被災した市民への見舞金や貸付制度、税の減免など各種支援施策の市民への周知について広報特集号を発行すべき
つのだ:災害援護資金の貸付けについて、償還期間等の延長、利率の変更、償還の免除の拡大など、当初、市民にお知らせした内容が変更された。
震災被害に対する見舞金や貸付制度、税の減免など各種の支援策については、4月15日付け「広報ふなばし」でメニューが紹介されている。このなかで例えば災害援護資金の貸付については、申請期間が6月30日までとされているが、その後、期間は平成30年3月31日までと変更になっている。この支援メニューの一覧では書かれていないが、液状化等による被害を救済するため罹災判定の基準が見直されたことに伴い、被災者生活再建支援制度をはじめ災害見舞金など対象となる要件が掲載当時とは変わってきている。それらの情報については少なくとも広報ふなばしには掲載されていない。市税についても、例えば雑損控除の特例については6月1日付け号の広報ふなばしの情報ひろばにお知らせが載っているが、固定資産税の減免の適用基準が緩和されたことについての情報は少なくとも広報には掲載されていない。
「地震発生から1か月」と題して3ページにわたる特集を組んだ4月15日付けの「広報ふなばし」では最初の面で市内の被害状況を大きく載せているが、その数字は住宅の全壊5棟、半壊5棟、一部損壊218棟としている。市のホームページで報告されている被害の数字(6月3日現在)は個人住宅で全壊11件、大規模半壊78件、半壊149件、一部損壊732件と膨れ上がっている。4月の時点では支援メニューの対象とならなかったものが、その後の見直しで対象となる被害が増えたということだが、要件の見直し等についての情報提供は確かに市のホームページでは迅速に詳しく行われている。問題はホームページ等を見ない、あるいは見られない高齢者世帯等への周知が十分に行われているのかどうかということだ。
ホームページ以外の市民への周知方法としては、市の窓口にチラシを置くほかには、罹災証明の交付を受け持つ税務部からの情報をもとにお知らせを送付しているとのことだが、判定基準の見直しで対象が増えるなかで、罹災証明の交付を願い出ていないために、支援を受けられるにも関わらず、知らないために受けられないということが生じるのではないかという懸念を抱いている。
今議会にこれから市の被災者住宅補修等助成事業といった新たな支援メニューも提案されることになっており、市民への制度の周知を図るためにも、震災の各種支援メニューを網羅的に紹介する特集号を是非とも発行すべきと考えるがいかがか。
答弁:4月15日号を震災特集号として、被災された方への支援策を紹介したが、その後、新たに設けられた制度や更新された情報などもある。また、今議会で審議していただいている市独自の被災者住宅補修等助成事業など、新たな支援策が正式に決まった時点で、これまでの被災者支援策と一体化して紹介する紙面作りを行ってゆく。
■全ての手続きが一つの窓口でできるように
つのだ:支援施策の迅速な実施と、市民の利便性向上の観点から、可能な限り手続きがひとつの窓口で完了するようワンストップサービスについても是非考えてもらいたいがいかがか。
答弁:被災者が判断に迷うことなく、諸手続き円滑に進めるため、ワンストップサービス窓口を設けるべく、現在、新たな支援施策に関連する建築部や、り災証明に係る税務部、低所得者への貸付けを行っている市社会福祉協議会に声をかけている。7月の早い時期にはワンストップ窓口を設ける方向で協議を進めてゆく。